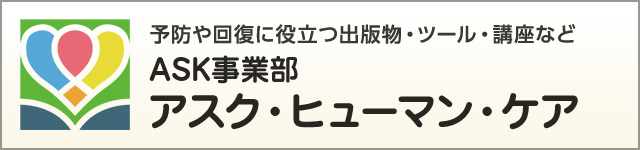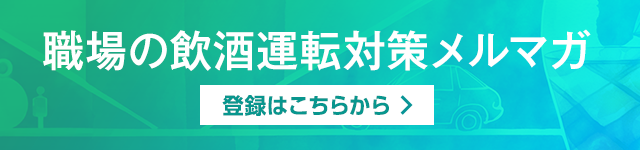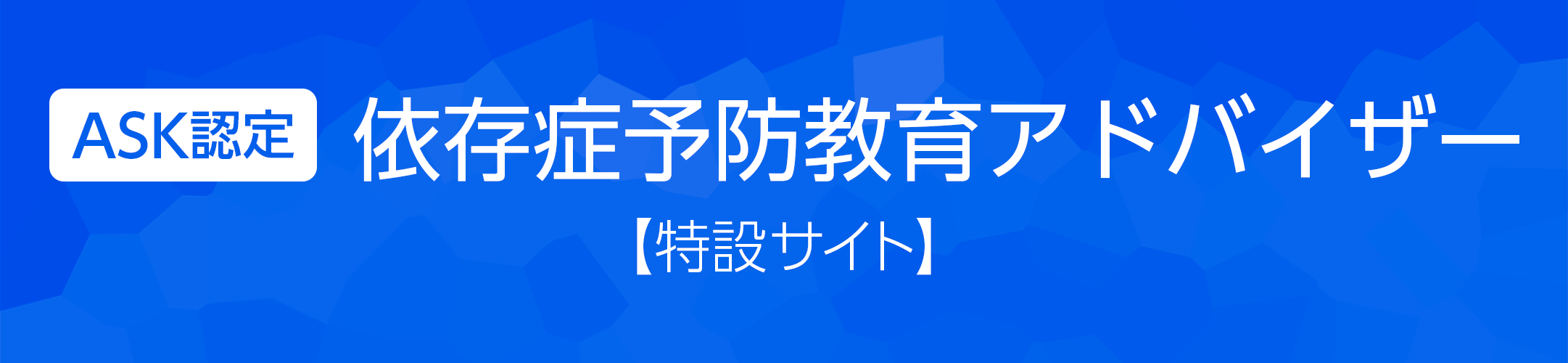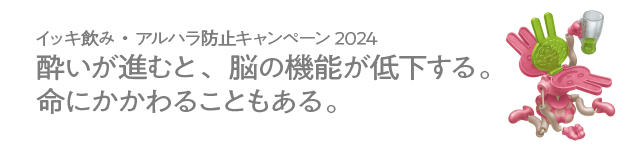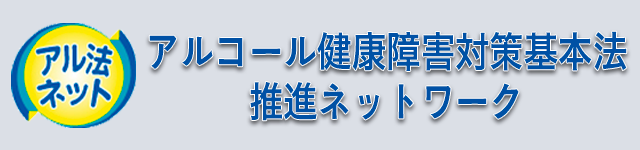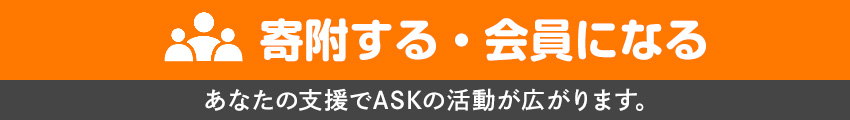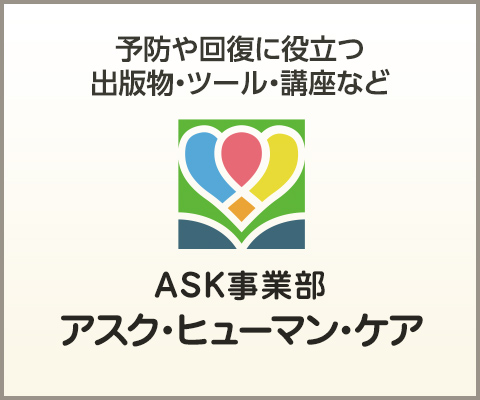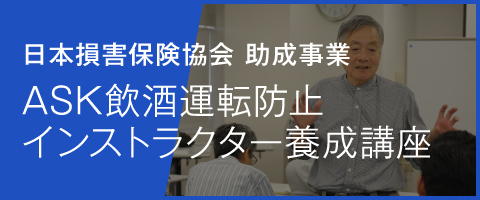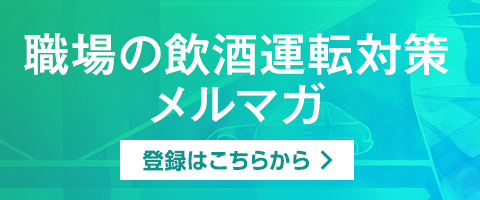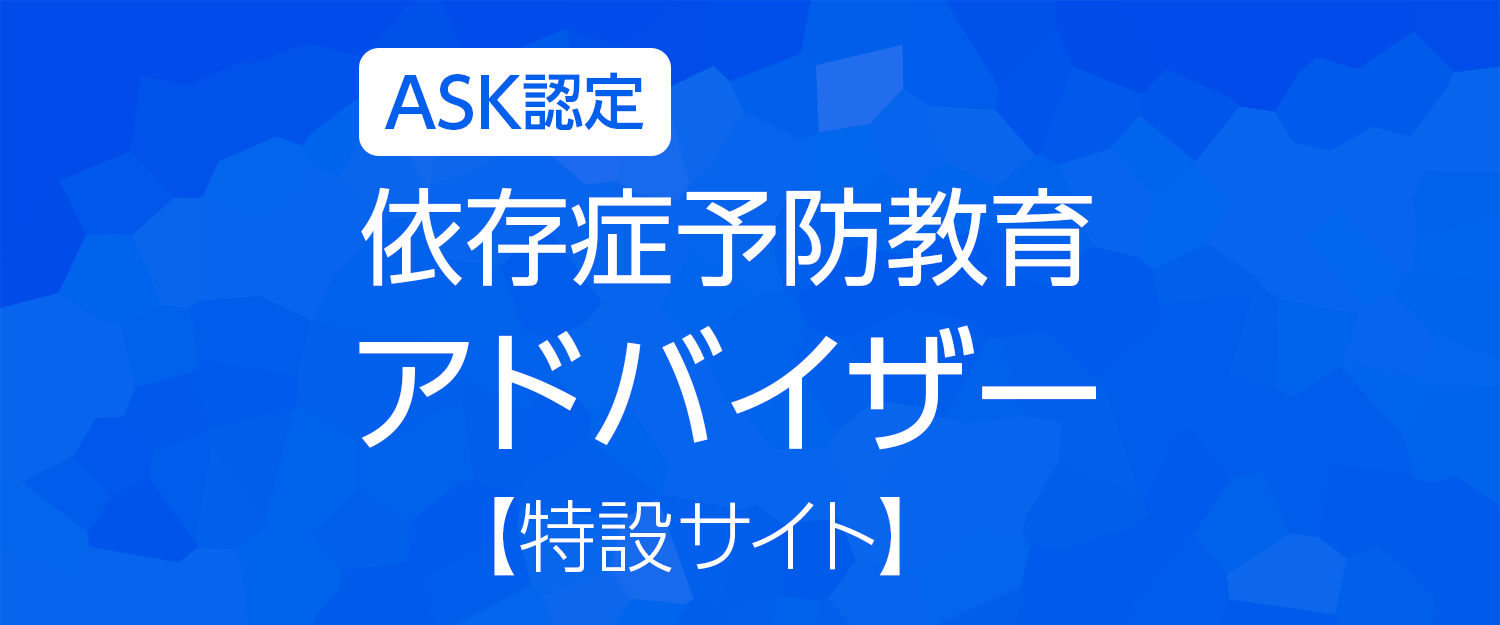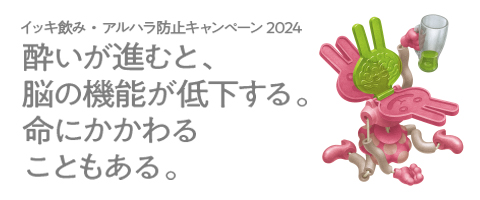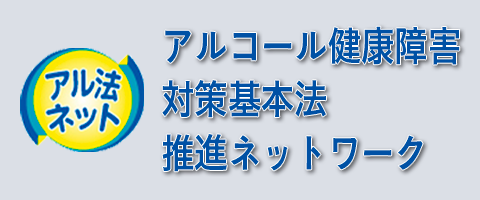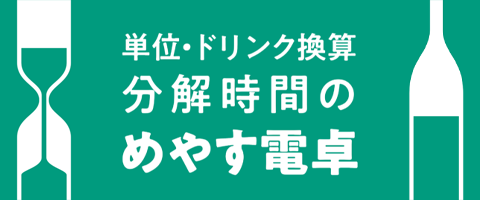2024年6月18日
特定非営利活動法人ASK
メールやお電話で、さまざまなご意見・お問い合わせをいただいていますので、申し入れ書と内容は重複する部分もありますが、ASKの考えを改めてお伝えします。
個別のご意見・お問い合わせに対する回答は控えさせていただきますので、ご了承ください。
アルコールは単なる嗜好品ではなく、含有されているエチルアルコールには、致酔性・依存性・発がん性・胎児毒性などさまざまなリスクがあるため、世界的には2010年5月にWHOが「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」を採択しており、日本でもビール酒造組合や日本洋酒酒造組合がグローバルな酒類産業と連携して賛同を表明しています。
・WHO「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」
https://alhonet.jp/pdf/who2010.pdf
・ビール酒造組合
https://www.brewers.or.jp/release/pdf/100520who-rele.pdf
https://www.brewers.or.jp/release/kaiken-sen.html
・日本洋酒酒造組合
https://www.yoshu.or.jp/pages/60/
この世界戦略を受けて、日本においても、2013年12月に「アルコール健康障害対策基本法」が成立、酒類事業者の責務も以下のように規定されています。
第6条 酒類の製造又は販売(飲用に供することを含む。以下同じ。)を行う事業者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努めるものとする。
・アルコール健康障害対策基本法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC1000000109_20220401_430AC0000000059
酒類の広告については、酒類業界団体が共同で定めた「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」(昭和63年12月9日制定、令和元年7月1日最終改正)において、酒類事業者は「20歳未満の者の飲酒や飲酒運転など法律を逸脱する行為のほか、不適切な飲酒を防止し、適正な飲酒環境を醸成するなどの社会的責任を果たしていく必要がある。」とし、酒類事業者は広告・宣伝や酒類容器の表示にあたり、法令を遵守することはもとより、それに加え、自ら尊重すべき基準としての自主基準を定め、その遵守に努めるだけでなく、同基準の不断の見直しを行なうなど社会的な要請へのさらなる対応を期する必要がある、との基本的な考え方を示しています。そして、同自主基準において、公共交通機関についての自主規制項目として「(イ)車体広告、(ロ)車内独占広告、(ハ)自動改札ステッカー広告、(ニ)階段へのステッカー広告(駅改札内を対象)、(ホ)柱巻き広告(駅改札内を対象)」が明記されています。
・酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準
https://www.rcaa.jp/standard/pdf/jishukijun.pdf
これは、駅や電車が不特定多数が利用する極めて公共性が強い場であることにかんがみて、乗降客には20歳未満の青少年も含まれ、ドクターストップで禁酒・断酒中の人や飲めない体質の人もいること、早朝からの通勤・通学や、勤務中の移動時に酒類広告はなじまないことから、意図せず目に飛び込む「強制視認性」のとくに強い上記の手法を、2005年に自主規制の対象としたものです。
今回の事例のように、駅名自体を酒類の商品名にして駅空間の仕様を変更することや、プロモーションの一環として駅ホームで酒場を営業することは、当時はまったく想定していなかったため、自主規制項目に規定されていません。
2020年の時点で、ASKなど関連団体が、次々と開発される新たな交通広告手法にも対応できるように、規制すべき項目を列挙するだけでなく、包括的な規定に改正するようビール酒造組合に要望しており、サントリーを含む大手数社とは個別にも話し合いを行ない、認識の共有をしました。ビール酒造組合に要望したのは、大掛かりな交通広告を行なうのは同組合に属する大手数社に限られていたためです。
しかしコロナ禍でもあり、業界全体での自主基準の改正は行なわれませんでした。
ASKは酒類のマーケティングのすべてを否定しているわけではありません。
ただし致酔性・依存性・発がん性・胎児毒性などアルコールの特性を考慮して、マーケティングの行き過ぎを防ぐことは必要だと考えており、酒類業界とは40年を超えるやりとりを続け、共通認識を築いて参りました。
そのプロセスの中で、大手酒造会社は企業の社会的責任(CSR)としてアルコール関連問題に対応する部署を設置し、酒類業界全体としても自主基準を設けるなどの自主努力をされてきました。酒類自動販売機の自主撤廃、お酒マーク、妊産婦向けの警告表示、テレビCMの時間規制、喉元アップやゴクゴクの効果音をなくす、出演は25歳以上にするなどのCM自主規制もその一環です。
サントリーでは、上記の経緯を踏まえ、駅名に酒類の商品名を使うといった今回のプロモーションについては行き過ぎがあったと判断されて、自主的に看板の早期撤去などの対応をされたと理解しています。
ASKとしては、交通広告に関する業界自主基準が包括規定に改正されていなかったことが、今回の問題を引き起こした要因と考えていますので、酒類業界に対して引き続き自主基準の改正を要望していきます。